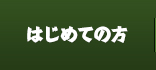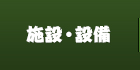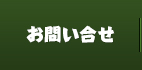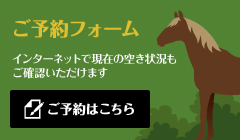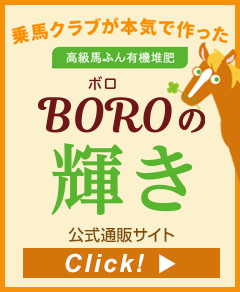初心者に必要な乗馬用品とは?基本的な人装品と馬装品について解説!

これから乗馬をはじめるにあたって気になることとして、どのような乗馬用品があり、初心者は何からそろえていけばいいかということが挙げられます。安全・快適に乗馬をおこなうには、乗馬の技術も大切ですが、乗馬用品がしっかりそろっていないことには実現できません。
本記事では、人と馬、それぞれに必要な乗馬用品について紹介します。事前に乗馬用品の知識を得ておくことで、初回の乗馬レッスンもスムーズに進むでしょう。
乗馬とは
一般的に、乗馬クラブでの乗馬とは、趣味や余暇を楽しむことなどを目的とし、馬に乗ることです。乗馬用品には人が身に着ける「人装品」と、馬が身に着ける「馬装品」があり、どちらも馬に扶助(合図)を出したり、馬とのコミュニケーションを図ったりする上で必要不可欠です。
乗馬は一見すると優雅で運動量も少なそうですが、実際は消費カロリーが多い有酸素運動で、とくに腰回りのインナーマッスルが鍛えられ、姿勢改善に効果があります。
馬の種類は大きくわけて、軽種馬・重種馬・中半血種・日本在来種・ポニーなどがありますが、軽種馬や中半血種のうち、温厚で扱いやすい種が、乗馬用の馬として活躍しています。
初心者がそろえるべき人装品
乗馬を楽しむためには、乗馬専用のものを身に着けることが大切です。以下に紹介する人装品は、どれも安全や乗馬技術にも関わるアイテムばかりですので、自分のサイズに合ったものをしっかりそろえましょう。
ヘルメット
ヘルメットは、安全面からも乗馬用のものを着用しましょう。ヘルメットを選ぶ際には、まず頭のサイズを調べておき、購入先では丈夫さ・通気性・軽さ・かぶり心地などをチェックしてください。ダイヤルやアジャスターで3方向のサイズ調整ができるタイプは、頭の高さや前後左右の幅をほどよくフィットさせることができます。インナーパッドを取り外せるタイプは、洗濯ができて衛生的です。
エアバッグベスト
落馬の衝撃から体を守るために着用するのが、エアバッグベストです。鞍につないだ伸縮ワイヤーが外れた瞬間、ベストに内蔵されたカートリッジボンベが作動し、首・胸・脇・背中・腰・お尻などをカバーするエアバッグが膨らむ仕組みです。乗馬用の馬の体高は140~170cm程度あり、その高さから落馬することを考えれば、着用義務の有無に関わらず、エアバッグベストを着用しておくべきでしょう。
天城ホースビレッジではレンタル装具一式の中にエアバッグベストも含まれています。
グローブ
乗馬の際は、手綱と人差し指や薬指あたりに、断続的な摩擦が生じます。そのため、乗馬用のグローブでないと、擦れた部分にすぐ穴が開いてしまうのです。
また、騎乗中は馬の口から伝わる微妙な動きを、ハミ(馬の口に装着する金属製の道具)から手綱を通じ、グローブで感じ取る必要があります。このとき、手綱を強く握りしめていては、その動きを感じ取れません。グローブにグリップ力があれば、手に力を入れることなくしっかり手綱を保持したまま、馬の繊細な動きも感じ取ることができます。このように、耐摩耗性やグリップ力に優れているのが、乗馬用のグローブです。
キュロット
乗馬用のズボンがキュロットで、耐久性や伸縮性がありフィット感にも優れています。フルグリップタイプは、お尻や太ももから膝の内側部分にグリップが付いており、立ったり座ったりなど鞍の上での動作や姿勢をサポートしてくれます。このタイプは初心者にもオススメです。ニーグリップタイプは、膝の内側のみにグリップが付いており、障害馬術用です。
ブーツ
長靴(ちょうか)を履くか、ショートブーツとチャップスを組み合わせて履くかのいずれかの状態で乗馬します。これらを選ぶ際に重要なのが、フィット感です。長靴のブーツ部分は、底面のサイズ・足の甲の高さや幅などを、筒部分は、丈の長さやふくらはぎ周りのフィット感をチェックしましょう。
少しだけ余裕があるサイズが理想ですが、大きすぎると、脚(きゃく・騎手の膝より下の部分)で馬にさまざまな扶助を出すときに、繊細な力加減がしにくいでしょう。チャップスは膝下から足首までをガードする巻き革で、ショートブーツの上に装着します。
天城ホースビレッジのレンタル装具はショーブーツとチャップスを用意しています。
基本的な馬装品
馬に装着する馬装品は、馬に扶助を出すためだけでなく、人と馬の安全性も高める役割があります。馬装品(馬具)を取り付けることを「馬装する」といいますが、馬装するにはその馬の特徴や個性、痛がっていないかなどを見極める必要があり、ある程度の経験やコツが必要です。
鞍(くら)・ゼッケン・腹帯
鞍は、馬の背中に乗せる馬装品で、簡単にいうと、馬に乗るための脱着式の椅子です。鞍を装着することで、騎乗中のバランスがとりやすくなり、人と馬の安全性も確保できます。足を置く部分は、鞍の左右に吊り下げてある鐙(あぶみ)です。
ゼッケンは、鞍の下に敷くマットのことで、馬への負担を減らし、鞍を安定させる役割があります。それら鞍とマットを固定するベルトが腹帯です。腹帯を締める際、馬が嫌がる場合もあるので、ゆっくり締めるなど調整や経験が必要です。
ハミ・手綱・頭絡(とうらく)
馬は、人間の奥歯にあたる部分に歯が生えません。その空いた部分にハミをくわえさせます。ハミの左右に付いた2つのハミ環を通してつながっているのが、頭絡と手綱です。
奥歯にあたる部分に歯が生えないのではなく奥歯は人間と同じ数だけ存在します。正しくは馬は面長なため奥歯と犬歯の間に歯の無い空間が存在していて、その部分にハミをくわえています。
頭絡は馬の頭から顔の部分にかけて装着される細い革ベルトで、ハミが馬の口の中で適切な位置を維持できるよう、長さが調節されています。騎手は手綱を通して、馬に方向転換や停止の扶助を出し、それがハミを介して馬の口に伝わります。
まとめ
乗馬用品には、人装品と馬装品があり、これらに求められるのが、フィット感・安全性・耐久性・適切な長さや位置などです。初心者がそろえるべき人装品には、ヘルメット・エアバッグベスト・グローブ・キュロット・ブーツなどがあります。また知っておくべき基本的な馬装品には、鞍・ゼッケン・腹帯・ハミ・手綱・頭絡などがあり、馬が不快にならないよう、それぞれの馬に合わせた馬装が必要です。
「天城ホースビレッジ」は、静岡県賀茂郡にある乗馬クラブです。「日本一敷居の低い乗馬クラブ」をコンセプトとし、ビジター料金で、子どもからベテランまで、それぞれのレベルに応じたマンツーマンの乗馬レッスンを提供しております。ハンディキャップをお持ちの方もぜひご参加(←ご相談)ください。
乗馬体験では、ヘルメット・グローブ・ボディプロテクター・ブーツなど乗馬に必要な装具はレンタルできますので、動きやすく汚れてもよい長袖やデニムやチノパンなどの長ズボンをご用意ください。
ご予約はホームページの予約システムより24時間空き状況の確認と予約の申し込みが可能です。
また、乗馬レッスンの後は、カフェ・クラブハウス・温泉施設などでくつろげますし、素泊まりもしていただけます。乗馬に興味があれば、お気軽にお問い合わせください。